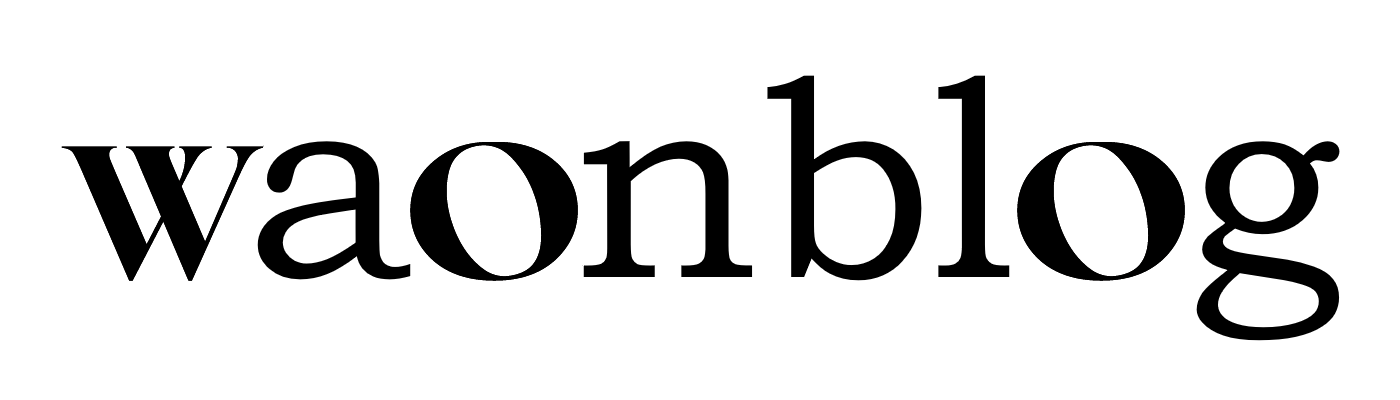映像作品の中で「歌うシーン」が頻繁に登場する「ディズニー作品」。
「ミュージカルアニメーション」などといわれることもありますが、「突然歌い始めるシーン」は、日本のオリジナル作品にはあまりなじみがありません。
ディズニー作品は、なぜ「歌う」のでしょうか。それを紐解くために、1作品ずつ分析していきます!
今回は「くまのプーさん(Winnie-the-Pooh)」をみてみましょう。
もくじ
参考資料
考察するにあたって、以下の資料を参考にして進めていきます。
書籍「英語で読むクマのプーさん」
「Winnie-the-Pooh」の原文を左ページに、その翻訳を右ページにレイアウトしている、ユニークな書籍です。
脚注には、少し難易度の高い英単語の簡単な訳も乗っていて、英語の勉強用に利用できます。
ただ、この書籍の優れているところは、「英文」と「翻訳」のすばらしさ。
英文には、難しい単語はほとんど掲載されていないのに、”口語”や”詩的”な表現が多く取り入れられていて、実用的な英語として楽しむことができます。
また翻訳も、まるで日本語版の書籍のように、とても流れるような素敵な訳をされています。かつ、世界観を壊さない、やさしい言葉遣い。
「詩的な英文」と、「世界観を壊さない翻訳」で、”こんな訳し方するんだ!”と驚いて、「アカデミックな英語の勉強」しかしていない方が手に取ると、衝撃を受けると思います。
- 原著者:Alan Alexander Milne
- 翻訳:牛原眞弓
- 出版:IBCパブリッシング株式会社
“Why do yo want a balloon?” you said.
Winnie-the-Pooh checked that nobody was listening. He put his paw to his mouth, and said in a whisper: ‘Honey!’
“But you don’t get honey with balloons!”
“I do,” said Pooh.「どうして風船がほしいの?」と、きみが言います。
(引用元:英語で読むクマのプーさん)
ウィニー・ザ・プーは、だれもきいていないか確かめました。そして口に手を当てて、小さな声で言いました。「ハチミツだよ!」
「でも、風船でハチミツなんてとれないよ!」
「ぼくなら、とれるんだ」と、プー。
ディズニー くまのプーさん(完全保存版)
ディズニーの、アニメシリーズ 元祖 「くまのプーさん」です。
いくつかシリーズがありますが、今回はここに収録されている、「プーさんとはちみつ(1966年)」を紐解いていきます。
- 公開:1966年(日本1967年)
- ピックアップ作品:Winnie the Pooh and the Honey Tree(プーさんとはちみつ)
- 監督: Wolfgang W. Reitherman
- 音楽:Robert B. Sherman、Richard M. Sherman
作品の成り立ち
書籍「Winnie-the-Pooh」
原作者の「アラン・アレクサンダー・ミルン」は、1882年にロンドンで生まれた、イギリス児童文学作家です。
「Winnei-the-Pooh」は、妻の「ドロシー・ド・セリンコート」との間に授かった「クリストファー・ロビン・ミルン」の為に書かれた1926年発表の作品でした。
初めは「新聞」に掲載、その後のシリーズが「マガジン」に掲載され、その後まとめられた書籍は大ヒットとなったそうです。
作品の冒頭には、妻へ向けたメッセージも込められていて、作品のあたたかさは、彼の「家族愛」からきているものなのかもしれません。
この作品は、世界中に愛されて、30カ国語に翻訳されています。
彼が実際に執筆したのは、「Winnie-the-Pooh」と「The House at Pooh Corner」の計「20編」だけでした。その後彼は「息子」のことを想い、「児童文学」から身を引いたそうです。
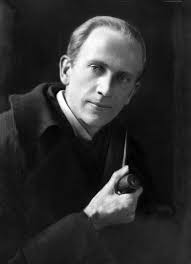
ディズニー「Winnie the Pooh」
「Winnie the Pooh」は、書籍が出版した当時からしばらく、別のキャラクターライセンス事業者が取得していました。
Walt Disney Companyは、1961年にライセンスを取得。1966年に「プーさんとはちみつ」が公開されました。
監督「 Wolfgang W. Reitherman 」
アニメ版の監督(プーさんとはちみつ)は、 Wolfgang W. Reitherman (ヴォルフガング・ライザーマン)で、「ディズニー ナインオールドマン」と呼ばれる、ディズニー初期のアニメーターの一人でした。
「白雪姫」「ピノキオ」「ファンタジア(春の祭典)」「ダンボ」なども担当していました。
音楽「 Robert B. Sherman、Richard M. Sherman 」
音楽担当の「 Robert B. Sherman、Richard M. Sherman 」の二人は、「シャーマン兄弟」と呼ばれていて、ディズニーの初期の作品の音楽をほとんど担当していました。
「メリー・ポピンズ」「ジャングル・ブック」「シンデレラ」などの他に、「スヌーピーの大冒険」という、グラミー賞ノミネート作品の音楽も担当しました。
世界で最も再生されている音楽「イッツ・ア・スモール・ワールド」も、彼らが作曲を担当しました。
くまのプーさんはいつ歌う?
原作に「歌のシーン」がある
「Winnie-the-pooh」は、もともと歌うシーンがあります。
例えば、以下のようなシーンで歌われます。
- ハチミツを求めて プーが木に登りながら 歌うシーン
- ハチミツを求めて プーが風船で飛びながら 歌うシーン
- プーが散歩をしながら 昔作った音楽を思い出して 歌うシーン
内容を見ていると、プーの気分がよくなった時に、プーの頭の中で歌が自然にできて、それを口ずさんでいるように思えます。
作詞作曲は、プー。
歌う前にストーリーテラーが、「新しい歌ができました」というのです。
かわいらしくて、大好きなシーンです。
Isn’t it funny
How a bear likes honey?
Buzz! Buzz! Buzz!
I wonder why he does?おもしろいだろ?
(引用元:英語で読むクマのプーさん)
クマは こんなに ハチミツが好き。
ブン! ブン! ブン!
どうして こんなに 好きなのかな?
アニメで「歌う」のはこんなとき
アニメシリーズの第一作「 プーさんとはちみつ 」は、書籍のチャプター1~2までの内容を、アニメ用に組み替えて制作されています。ここで挿入されている「歌」は以下の6曲です。
- ①くまのプーさん
- ②おいっちに、おいっちに
- ③おなかグーグー!
- ④小さな雨雲
- ⑤物より心
- ⑥おなかグーグーⅡ
30分ほどのアニメーションの中に、6曲もの歌が挿入されている「くまのプーさん」。
書籍のなかでは、「気分のいい時に歌を歌うプー」という内容でしたが、アニメーションではそれを膨らませて、歌をより沢山ちりばめています。
一曲一曲とても効果的な使われ方をしています。改めてまとめていきます。
①くまのプーさん
- タイム:2’00”
- シーン:オープニング
- 内容:本が開き、プーの仲間たちが初めて登場します。コーラスの歌で、仲間たちの紹介をして、「くまのプーさん」のテーマの提示も行われます。
- 原作での歌の有無:無し
作品のオープニングを飾るシーン。映像作品などでは、このオープニングにキャッチ―な音楽を付けることで、映像作品をより「記憶に残る」ものに仕上げる、劇伴的な技法があります。ここでも、「くまのプーさん」のメインテーマをしっかりと歌い上げて、視聴者の耳にメロディを届けています。
②おいっちに、おいっちに
- タイム:4’00”
- シーン:プーの体操
- 内容:お腹を空かせるために、 「いち にい さん しい 体操だ」と口ずさみながら、 プーが体操を始めます。
- 原作での歌の有無:有り
書籍にある「歌のシーン」をアニメーションとして構成しなおしています。
③おなかグーグーⅠ
- タイム:6’20”
- シーン:プーが木を登っている
- 内容:ハチミツを求めて、プーが木を一生懸命りながら、「ハチミツが待ち遠しい!」とうきうき歌います。でも、ハチに邪魔されて木から落っこちてしまいます。
- 原作での歌の有無:有り
書籍にある「歌のシーン」を再現したもの。歌詞こそ異なりますが、世界観をうまく表現した歌になっています。
④小さな雨雲
- タイムコード:10’30”
- シーン:プーが風船で飛んでいる
- 内容:ハチミツを求めて、プーがクリストファーロビンからもらった風船を手に、ぷかぷか浮きます。「彼は雨雲になってハチをだまずんだ」といって、体を泥んこの真っ黒に染めて、この歌を歌います。
- 原作での歌の有無:有り
このシーンも、書籍に歌のシーンがあります。「歌いださずにいられない」とプーは書籍で歌っています。
ぼくはただの雲
(引用元:くまのプーさん 完全保存版)
蜜のそばに浮かぶ
ああ ぼくは小さな雲
どうぞ気にしないで
⑤物より心
- タイムコード:24’00”
- シーン:詰まったプーをみんなで助け出す
- 内容:ハチミツを食べすぎて、ラビットのうちの入り口に詰まったプー。やっと痩せて、抜け出せそうになった。「えい おうおー」と森のみんなでうたいながら、プーを引き抜いて、助け出してあげます。
- 原作での歌の有無:無し
このシーンで歌うのは、アニメーションのオリジナルです。森の仲間たちみんなで歌う、一つの山場のシーン。 作品も終盤に差し掛かった場面で、音楽でもそろそろ終わることを暗示させるような作り方がされています。これがあるのとないのとでは、視聴者の満足度が一気にかわることでしょう。
⑥おなかグーグーⅡ
- タイムコード:25:30
- シーン:プーがハチミツを食べながら歌う
- 内容:ハチミツがお腹いっぱい食べれる場所にたどり着いて、プーがハチミツを夢中で食べながら歌います。
- 原作での歌の有無:無し
最後の結末のシーン。作曲技法として、今までに出てきた楽曲を”リプライズ”する(編曲されて再び登場させる)ことで、作品自体にまとまった感覚を与える劇伴の技法でもあります。プーはほとんど「むしゃむしゃ」ハチミツを食べて歌詞を持たない歌を歌っていますが、効果的に音楽が挿入されています。
プーは原作の雰囲気にそって歌う
「くまのプーさん」の場合、歌うときは、「原作に歌のシーンがあったとき」と、オープニング・エンディングなど、「記憶にとどめるためにメロディ必要な時」の、2パターンで、音楽を入れているようでした。
映像作品における音楽の役割として、「記憶につなげる」というものがあります。(もちろん、絶対ではありませんが。)
その音楽を聴いただけで、頭の中に映像を思い出すといったような経験を、されたかたもいるのではないでしょうか。そんな、人のこころを動かすような音楽のあり方を、作品の世界観を表現することと共に常に探って、人の記憶に長くとどめてもらうことが、劇伴作曲家の使命だと私は思っています。その答えを持っているなと感じる作曲家が、ディズニーには多くいらっしゃいました。
世界観を音楽で表現しながら、しっかりと記憶につなげてあげるための、「くまのプーさん」の音楽としての一番の答えが、この映像作品だったのではないでしょうか。
いかがでしたか?
ちょっぴり変わった目線での作品解説でしたが、他の作品も今後紐解いていきますので、是非投稿をチェックください♪
(Twitter フォローもお待ちしています!)